外壁塗装の見積もりを依頼したのですが、 A社は、外壁はシリコン系、金属屋根はウレタン系、 B社は、外壁も金属屋根もシリコン系で出してきました。 B社にウレタンよりシリコンの方が上だと言われました。 それはネットなどでざっと見た感じでも、そんな感じに見えますが、 もしかしたら、「金属屋根はウレタン系の方が向いてるという事もあるのかな(あえてウレタン系で計算してきた)」と思いました。 いかがでしょうか?
Yahoo!知恵袋より引用
クレームはペンキ屋さんのせい…?
外壁塗装におけるクレームは、
塗装業者にだけに責任を負わせがちです。
事実、私たちの塗装業者は、全力で良い仕事をしても、
実際に塗った塗料の性能のせいで評判を落とすことあります。
以前、
「お客様にも喜ばれる、納得の行く仕事をやったぞ!」
と思うことができた現場がありました。
そう思って数年がたったある日…
「屋根がもう色あせてきたけど、どういうことなの!!」
とお客様からお叱りの声を頂いたことがあります。
その現場で使用した塗料は、
皆さんも聞いたことのある有名なブランドで大手塗料メーカーのものです。
使用したのは、当時メーカーさんがおオススメしていた、
遮熱シリコンの屋根用塗料でした。
もちろん私には職人として、良い塗料を見極めて、
お客さんに提供する義務があります。
そして、メーカーがすすめる塗料を簡単に
信用してしまった落ち度があります。
しかし、塗料を比べることをこれまでしてこなかった
塗料販売店さんや、塗料を作って販売してきた
メーカーさんには、工事の品質の責任は全くないのでしょうか?
現実としてクレームを受けるのは、末端の職人です。
塗布量や乾燥時間など、
すごく品質にこだわって作業を行っ結果なのに、
こういったクレームが事実起こり、
そしてそのお客様とその後
すごく話しにくくなったことを覚えています。
「本当に良い仕事をしたのに、
なんでこんな目にあうのだろう…。」
こう思ったことのある職人さんや施工業者は、
本当に多いと思います。
それ以来、私は例え大手の業者であっても
メーカーがすすめる新製品には、
安易に手を出さないようにしています。
そして、このページを読んでいらっしゃる読者の方にも、
なるべく実績のある、安心できる塗料を選ぶことを
おススメします。
この点を踏まえて、塗料販売店さん勤務歴35年のOさんと
「良い塗装業者の見分け方」について対談しました。
塗料卸業30年のベテラン、Oさんとの対談インタビュー
横井:一番最初にOさんに聞きたいと思ったのは、塗装業者選びについてです。一般の方は、塗装工事の際にどこの業者を選んでいいかわからないと思います。Oさんは、塗料販売の業界経歴が長いじゃないですか。私が小学校の時にはもうやっておられましたよね。塗装業界で仕事をされて実質何年くらいですか?
Oさん:35年くらいにはなるんじゃないかな。
横井:うちの会社の創業とほぼ同じくらいですね。塗料を販売すると、職人さんからもたくさん情報が入ってきますよね。色んなつながりから、クレームとかも見たり聞いたりしていると思います。Oさんからみて、一般の方が塗装業者を選ぶコツってありますか? そして良いアドバイスはありますか?
Oさん:信頼性が大事だね。本当にしっかりとした施工をやってくれるかどうかだよ。例えば3回塗りのときに、本当に3回塗ってくれるかどうか。必ずやってくれるところが信頼できる塗装業者だね。
横井:一般の人は、2回塗っても3回塗っても見た目もほとんど同じなので、わからないですよね。多少色を変えて塗らないと、何回塗ったかなんてわからない。Oさんがもし、例えば親戚の人など近い人に業者選びでアドバイスをするなら、「この点に注意しろ!」っていうようなことはありますか。
Oさん:信頼性の見極めかな。3回塗りなら3回塗り、2回塗りなら2回塗りと予定通りの作業をするかどうか、しっかりと計量するかどうかなど、信頼できるところかどうかの見極めが大事だとアドバイスするね。
横井:塗膜の厚みなども一般の方にはなんか分からないですよね。うちはちゃんと計量していますが、ネットで見たところ、経験を頼りに目分量でやっている方もいますし、しっかりとしていないところなどは全く計量していないようです。シンナーで塗料をのばされて誤魔化されたとしても、一般の方ってわからない。
Oさん:3年ぐらい時間が経ってやっとわかるくらいだね。そのくらいの時間がかかるんだよね、塗装の良し悪しがわかるためには。
横井:一般のお客さんにとっては、それだと怖いですよね。結局どうやって業者を選べばいいのかがわからないと思うんですよね。それについては、どう思いますか?
Oさん:よくあるのは、実績で何件やったか、地元でやっているかという話を聞くことですね。「どこどこの業者で施工をして、年数これくらい経ったら、状況はこんな感じだよ」という情報を集めるとより良いかも。小さい業者であっても、納得できるように写真で施工例を示してもらう。実際に施工を始める前には、デジカメで住まいの状況を撮影してもらい、割れている箇所などを写真で確認する。施工が終わった時にも写真を撮影して施工状態を確認する。自分自身が納得することが大切。
横井:まだどこでやるか悩んでいる人は、そういうことを施工と同時にしてもらえるかどうか、見積もり時に確認するといいですね。
Oさん:そうそう。そうすると間違いがない。
横井:業者の選択には悩むけれど、ハウスメーカーさんなら安心感があるかもしれません。
Oさん:塗装店は安いけれど信頼度が…といううようには感じるかもしれないね。
横井:最近お客さんと会ってよく感じるのは、インターネットで勉強されている方が多いということです。ハウスメーカーは結局下請けに出しているだけだから、マージン取られるだけでだということもわかっている。でもインターネット上には色んな情報が玉石混交で、お客様も、実際にどうやって施工業者を選べばよいか悩んでいる。
Oさん:大手は、車でいうとディーラーにあたります。高くてもクレームを出した時にはちゃんと対応してくれる。小さい塗装屋さんは、町の小さな車屋さん。そういう小さいところが、「うちはディーラーほど大きくはないけれど、ちゃんと対応しますよ。」「あなたのクレームにも対応してちゃんと直しますよ!」というのと同じで、塗装工事でも、「すぐアフターサービスに来ますよ。」という姿勢が伝わってれば良いんじゃないかな。
あとは、やっぱり近いと早く来てくれやすいよね。こういうことが信用につながる。施工業者にとってはその後の営業にもつながる大切なことだよ。」
横井:一般の人にアドバイスするなら、アフターサービスに来てくれるかどうかも大きな目安になるってことですね。
Oさん:メーカーなんかがやっている50年保証とかというものは、実際には保証はほとんどない。
「メンテナンスしますよ。」とは言うものの、
「見に来ました。だから、メンテナンス費をください。」という内容のものもある。それで、結局お金が掛かってしまう。
横井:塗料の保証書ってあるじゃないですか。あれは実際は色あせとかについて保証されているだけであって、ペンキの剥がれとかになると塗装屋さんの責任だから、関係ないんですよね。私たち施工する側としては、色あせの品質についても、しっかりと補償出してほしいのが本音です。いざ保証書を発行してと依頼すると、断られる事もけっこうあります。高い値段の塗料の割に、塗料の品質については責任を取らずを逃げることもあるように思えます。
Oさん:僕達販売店側からみたら、塗料の中で余って使わないものがあるね。しっかりと測っていない職人さんが多いから、余るはずのない硬化剤が余っている(※2液型では主剤だけが消費期限切れを起こし、主剤と硬化剤のバランスが崩れることがあります)。ということは、ちゃんと入れるべき硬化材の量が、誤っていることがあるんですよ。ごまかしているっていう感じではないんですけれども、測り方が曖昧。だからメーカーも保証しづらいのかもね。
横井:ところで話は変わるんですが、料理の食材とシェフの腕と一緒と同じで、塗装の品質も塗料と職人の腕じゃないですか。食材の選び方にあたる塗料の選び方って難しくないですか?
例えば、お客さんはフッ素とかシリコンとかの塗料があるなかで、何を選んだらよいのかが分からない。私たち業者は、フッ素がおすすめですと言ってもフッ素塗料にも沢山種類があって、
フッ素の含有量が少なくて実はシリコンより耐久性が低く、長期間もたない塗料もある。となると、実際問題、本当は何がいい塗料なのかはすごく難しい。
Oさん:それは業界としてして決まりごとがないことだね。
昔からそうで、どこどこのシリコンは1万円。他のところは3万円。何が違うのかというと、シリコンの含有量が違う。どっちがいい塗料かって聞かれると答えるのが難しい。塗料は年数が経たないと、結局は実績が出ないから。
横井:塗料の販売店さんは、料理の味を比べの様には塗料を比べることができないじゃないですか。タイムラグが長いから。「これの方がいいですよ」と言われても、本当に比較するには10年前まで遡らないといけない。それを踏まえたうえで、一般の人がいい塗料を選ぶとなると、やはり難しい。
Oさん:難しいよね。昔ならペンキが主だったけど、ウレタンになってシリコンになって。フッ素が長期間もちますよと言われても、本当のところは分からない。ウレタンでもいいし、シリコンでもいい。流行りだとラジカルなんかもある。」
横井:実際にどれが良いかわからないから、結局見積書に出てくる金額と財布の相談になりますよね。」
Oさん:そうなっちゃう。あとは、どれぐらい昔からの塗料で、
どれぐらい実績があって、安心できるかどうかも判断材料になる。また、施工業者が、今の塗料を知っているかどうか。今の主流の塗料の中で、実績としてこのシリコンが良いよ、このフッ素が良いよっていうような話が出てくることが望ましいね。
横井:やっぱり塗料をしっかりと知っている業者が良いということですね。メーカーのおススメを鵜呑みにしないで、年数がある程度たっている実績がある塗料が安心ですね。
横井:また話が変わるのですが、よく2液の方が長持ちするとか、溶剤系と水性だと溶剤系の方が長持ちするとか言われていますよね。でも、水性でも塗料によっては、塗膜がけっこう厚くなって長持ちするものもありますね。
Oさん:基本的には塗布量が多いかどうかって話ですね、耐久性は。色変化でいうと、溶剤の方が樹脂とかの関係で劣化が少ないかもしれない。
横井:色落ちですか。
Oさん:例えば水性シリコンと溶剤シリコンを比べると、溶剤シリコンの方が色落ちは基本少ないように思います。
横井:順番としては、艶落ちしてから色素が落ちる感じですよね。あと、現状の塗料では、シリコンとかフッ素とかがありますが、その特徴を一言でいうとどうなるでしょう。一般の方に説明をしようとすると、なかなか説明しにくくて…。樹脂だけでも、その他にアクリル樹脂やシリコン樹脂、ウレタン樹脂などもありますね。ウレタンといえば、例えばシーリング剤にも種類がありますが、そもそもどういうものなんですか。
Oさん:ウレタン樹脂っていう分類しかないね。中に入っている樹脂の配合量によって呼び方が変わるようだよ。
横井:イメージで言うとウレタンが柔らかくて、シリコンが紫外線に強くて。フッ素の方がより紫外線に強いけど柔軟性が悪くてひび割れがし易いとか、一般のお客さんに説明しにくいなって。
Oさん:今の話、全部規定されているものではないからね。それに少しでもフッ素樹脂が入っていれば、フッ素塗料とうたってもいい。10年という長期間たった後に欠点が見つかったとしても、メーカーとしては販売し続けるとある程度は売れるからってのもある。
横井:「色あせたからどうしてくれるの!」ってお客さんに言われて困った経験のある業者さんも多く見かけます。」
Oさん:このメーカーのこの塗料はおかしいなどと具体的なことは言えないけど、本当に悪いものはごく僅かだよね。その点を考えても一般の方が塗料を選別するのってなかなか難しいんじゃないかって思う。塗装自体が、塗料だけでは成り立たないものだから余計にね。良い塗料もあれば、ちゃんとメーカーの規定通りに現場で計られないこともあるし。
横井:塗料を実際に塗る時の気温や湿度、配合率をちゃんと把握しているかを記録したものがあるといいですね。
Oさん:そういうのがあるかどうかってだけで、全然違うね。
横井:そういうのを自主的に提出してくれる業者さんを選んだほうが良いってことですよね。
Oさん:うちは工程ごとにちゃんと記録をとっていますよって。
経過写真も撮りますよって。
横井:うちはいま、それをアプリを使ってやっているんですけれども、お客さんにけっこう好評ですよ。あとでお見せしますね。
横井:ちなみにOさんが、遠方の親戚に「塗装業者をどうやって選んだらいい?」って聞かれたら、どうアドバイスしますか?
Oさん:実績かな。実績が信頼だから。料理屋の料理でも、美味しいとお客さんが来て、まずかったら来ない。そういう世界だから。
横井:結局はそうですね。
Oさん:地道にやっているところ、ちゃんとした工事をしたところは、10年くらいたってハガキで施工の案内を出すと、やっぱりお客さんは戻ってくるしね。塗りっぱなしで終わってしまう業者もあるけどね。
横井:やっぱり地道さは大切ですよね。
Oさん:続いてるのは理由があるんだよ。
横井:本日はお忙しい中、ありがとうございました。結局、続いていることが信頼に値するのかなって思いました。料理屋さんと一緒で、まずかったら業者は淘汰される。だから長い年月続いている業者が良いっていうこと。業者選びの本質かなと。
Oさん:こちらこそ、ありがとうございました。
以上対談終わり。
いかがだったでしょうか?
一般の方が塗料は何が良いかを見分けるのは、
本当に難しいです。でも、本当に良い塗料を見つける方法が無いかというと、そういうわけではありません。
実は本当に限られた職人ですが、長い年月をかけて、
地道に
塗料を塗り比べている方もいます。
そういった方をインターネットで調べあげて、
質問してみるのも良いかもしれません。
外壁塗装の見積もりを依頼したのですが、 A社は、外壁はシリコン系、金属屋根はウレタン系、 B社は、外壁も金属屋根もシリコン系で出してきました。 B社にウレタンよりシリコンの方が上だと言われました。 それはネットなどでざっと見た感じでも、そんな感じに見えますが、 もしかしたら、「金属屋根はウレタン系の方が向いてるという事もあるのかな(あえてウレタン系で計算してきた)」と思いました。 いかがでしょうか?
Yahoo!知恵袋より引用
外壁塗装のトラブル 業者に依頼して外壁を塗装しています。 施工開始から数日が過ぎてから気付いたのですが、契約した塗料よりランクの低い塗料の缶が持ち込まれていました。 業者に確認をすると、中身に間違いは無いとの説明でしたが、中身を入れ替えることは多々あるのでしょうか? また、すでに塗られてしまった塗料を個人が依頼して、契約した塗料の成分かを調べる機関はあるのでしょうか?
Yahoo!知恵袋より引用
外壁塗装の塗料について、どれがいいのでしょうか? アパートの外壁塗装の相見積もりでわからなくて困ってます。松竹梅の3段階でだしてもらいました。 1つは、地元で手広く工事を手掛けて、塗料を決めて、大量仕入れでコストダウンを図ろうとするのが売りのA社。B社は、最近近所に支店を開設し、研究熱心な所で自分の所の工事に自信を持っているようです。 A社は(外壁面積約397㎡で計算) 松 セミフロンスーパーマイルド 220万 竹ファイン4Fセラミック 210万 梅 スーパーユメロック 190万 コスパ級 ハイパービルロック 175万 B社 竹 超低汚染リファイン1000Si-IR 234万 梅シリコンREVO213万 松は、予算オーバーで提示をやめました。 A社は、手広い分安いですが、工事もスタートが遅く、管理が行き届くか心配ですが、個人事業主なのでコスパは魅力。 B社は社長が研究熱心で工事管理はしっかりしていそうですが、アステックへの思い入れがやや強いようで、値段は割高ですが、耐久性には自信を持っているようです。 A社は、どれも実験結果だけで、20年後のことはだれもわからないから、梅ランクで、充分ではないかとのスタンスでした。大量仕入れと仕事回転率の良さでコスパの良さを実現できるそうですが、、。 皆さんなら、どれが良いと思いますか?次回の塗装は15年以上は後にしたいです。
Yahoo!知恵袋より引用
外壁の塗料を選ぶときに知っておきたいこと
外壁の塗装を予定していますか?もしそうなら、この記事が参考になるかもしれません。今回は、15年以上長持ちさせるために、外壁の塗料を選ぶ際に知っておきたいことをご紹介します。この記事の終わりまでに、あなたは情報に基づいた意思決定を行うために必要なすべてを知っていることでしょう。
それでは、 15年以上の耐久性を持った外壁塗装にするための塗料を選ぶために知っておくべきことを学んでいきましょう。
外壁に必要な塗料のグレードは、 下から、アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素、無機が一般的になります。 次回の塗装を15年以上持たせる場合は、無機塗料を使用する必要があります。2液タイプの溶剤系がお勧めしております。水性よりは溶剤系、1液型よりは2液型の方が耐久性があります。 最近では、2度目の塗装の上にさらにクリアーを塗り、紫外線から塗膜を守る方法もあります。
塗料の 色の種類によっても、色褪せの速さが変わってきます。 赤とか黄色など鮮やかな色が入ったものは比較的色褪せがしやすいです。また濃い色のものの方が淡い色のものの方が比較的色あせが目立ちやすく、色あせも早いと感じやすいです。デザインを重視する必要もない場合は、なるべく色あせが起きにくい色を選ぶのがお勧めです。
塗膜の厚さも耐久性に影響を与えます。 あまりにも塗膜が薄い場合は塗膜の剥離等につながることもあります。夏冬の寒暖差による伸び縮みに塗膜が薄いと追従できなくなるからです。
下地が良い状態でなければ、その上に塗装することはできません。下地の状態が良くないと、 せっかく高級な塗料を塗っても、古い塗膜と一緒に剥がれてくる可能性があります。
ウレタン塗装は、最近ではあまり選ばれなくなった塗料ではありますが、外壁塗装にとって完全にシリコン塗装に劣っているかと言われると、そうではありません。シリコン塗装が主流の現在においても、あえてウレタン塗装を選択するケースがあります。今回は、そんなウレタン塗装についてご説明します。
ウレタン塗装は、ウレタン塗料という塗料を使用する塗装方法になります。ウレタン塗料は、耐候性がありつつ、低価格であることから、少し前までは主流の塗料となっていました。しかし、その後、シリコン塗料というウレタン塗料よりも耐候性が高く、価格もリーズナブルな塗料が登場したことによって、徐々に使用される機会が減少しています。
しかし、現在においても、ウレタン塗装が完全になくなったわけではありません。シリコン塗料よりも耐候性が劣りますが、その分、コストを抑えることができますので、例えば、雨樋部分のみをウレタン塗装をすることによって、トータルコストを削減する場合や、改装などを計画しており、長期間使用する予定ではないため、耐候性が低くても問題がないウレタン塗装を行うといった使い分けが可能となっています。
①水性塗料か溶剤(弱溶剤、強溶剤)か
ウレタン塗料は、塗料そのままで使用することはできず、希釈のための溶剤と混ぜ合わせる必要があります。この混ぜ合わせる溶剤によって水性、弱溶剤、強溶剤の3つのタイプに分けることができます。
(1)水性
ウレタン塗料を水で薄めるタイプの塗料です。塗料独特の匂いが少なく、作業が容易であるという特徴があります。 昔から水性塗料と溶剤系比較すると溶剤系塗料の方が耐久性が良いです。ウレタンは耐候性も低いので、 屋内での使用を除き、なるべく溶剤系の塗料を使用した方が良いです。
(2)弱溶剤
ウレタン塗料を薄めのシンナーで薄めるタイプの塗料です。水性に比べ、匂いは発生しますが、 水性塗料に比べ塗料の粘度があるため、密着度や耐久性が向上しています。
(3)強溶剤
ウレタン塗料を強めのシンナーで薄めるタイプの塗料です。他の2つに比べ、匂いが強く、人体や環境への影響もありますので取り扱いには注意が必要ですが、弱溶剤よりも高い密着度、耐久性があります。 仕上がりがなめらかで、ハケ目が目立たないなどきれいな仕上がりが特徴です。ただ臭いがきついため職人さんに与える影響は大きいです。
②1液型か2液型か
2液型は、塗料の缶と硬化剤の缶の2つから構成され、塗装の直前に塗料と硬化剤を混ぜ、そこに上記の希釈剤を入れることによって使用できるウレタン塗料です。2液型の塗料は、耐久性が高く、様々な場所に塗装できる一方で、混ぜたらすぐに使用しなければならず、余った分は後日使用できないといったデメリットが存在します。 一般住宅では下請けの職人さんが工事に来てくれることがよくあります。そこではしっかりと混合比率を守って職人さんが塗装してくれているかどうかも確認するポイントとして降ってます。秤をちゃんと使用しているかどうかそちらがポイントになってきます。
③1液型
1液型は、塗料の缶は1つだけで、そこに上記の希釈剤を入れることによって使用できるウレタン塗料です。1液型の塗料は、2液型に比べて価格が安く、残っても翌日、再度利用することはできますが、耐久性が低く、使用できる場所が限定されるというデメリットが存在します。 材料はシンナーで希釈されているため、余った材料が多すぎる場合は再利用はできませんが、現場ではそこまで希釈率に対する意識が低いためなので収まっています。
ウレタン塗装の耐久性は、一般的に5年~7年と言われています。現在、主流のシリコン塗装の耐久性は7年~10年ですので、それに比べると耐久性は低いといえます。1缶あたりのコストは、ウレタン塗料が5,000円~20,000円なのに対し、シリコン塗料は15,000円~40,000円となっており、費用対効果はウレタン塗料のほうが高いように見えますが、実際には外壁塗装の工賃等もかかるため、長期的に見た場合は、シリコン塗装の方がコストパフォーマンスは高いといえます。逆に耐久性が7年未満で問題ないのであれば、ウレタン塗装のほうがコストパフォーマンスは高いといえます。
①ウレタン塗装のメリット
(1)低価格
これまでの説明でも何度か出てきていますが、ウレタン塗装のメリットとして第一に挙げられるのは、その費用の安さです。ウレタン塗装は、数ある塗装の中でも非常に安価ですので、コストを抑えるには、真っ先に候補に上がる塗装方法となります。また、似たような価格帯のアクリル塗装よりも耐久性に優れており、使用できる素材が多くあるのもメリットとなります。
(2)塗料の種類
ウレタン塗料は、シリコン塗料が登場するまで、外壁塗装の主流でしたので、各メーカーから様々な塗料が販売されています。各メーカーが様々な工夫を凝らした塗料の中から最適な塗料を選択できるのもウレタン塗装のメリットとなります。
(3)使い慣れた職人さんが豊富
先程も記載した通り、ウレタン塗料は、昔から使用されている塗料ですので、ウレタン塗料を使い慣れた職人さんが多く活躍しているのもメリットの1つでしょう。多くの職人さんが使い慣れているため、塗装の品質が高く、安心しておまかせすることができます。
(4)ウレタン塗料の弾性
ウレタン塗料は弾性が高く、ひび割れが起きにくい特徴があります。例えば、木材などは時間の経過や水分の保有状況によって伸縮する特徴がありますが、弾性の低い塗料で塗装した場合、その伸縮に塗料が耐えきれず、ひび割れが発生していまいます。しかし、ウレタン塗料であれば、弾性が高いため、木材の伸縮に合わせて塗料も伸縮し、ひび割れが起きにくいというメリットがあります。 夏冬の寒暖差による雨樋の伸び縮みにも対応ができるのが特徴です。
②ウレタン塗料のデメリット
(1) 耐久性
こちらの何度が記載していますが、シリコン塗装に比べてウレタン塗装は耐久性が低いというデメリットがあります。耐久性が低いと、その分、塗り替えの頻度が増し、長期的にはコストがかかってしまうというデメリットとなります。
(2) 紫外線の影響
ウレタン塗装は、紫外線から建物を保護する力はありますが、塗料そのものが紫外線の影響を受けやすく、艶びけが早く起こることがあります。そのため、ウレタン塗料は紫外線が当たりにくい部分に適しており、屋根や直接紫外線を受ける外壁にウレタン塗料を使用した場合は、変色すること可能性が高いことに注意しなければなりません。
(3) 塗料の膨張
断熱材が入っている住宅が増加していますが、外壁に断熱材が入っている場合、外壁と塗料の間に熱がこもりやすくなります。この熱によりウレタン塗料が膨張してしまい、剥がれてしまうケースがありますので、断熱材が入った外壁への塗装には向いていません。
現在ではシリコン塗装が主流となっていますが、ウレタン塗装もメリットとデメリットをしっかりと理解した上で使用することで、現在でも有効な塗装方法となります。ウレタン塗装のメリットとデメリットについては、信頼できる業者さんに相談することでしっかり説明をうけることができますので、お気軽にご相談ください。
1液ウレタン塗料は、現在の外壁塗装においてはほとんど使われておりません。
現在見積もり時においては、アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素、無機塗料 とそれぞれ のグレードに分かれて見積に提案されると思います。その中でウレタン塗料は一昔前に比べ、見積もり時においても選ばれることが少なく、ヨコイ塗装でも実際に工事には使っておりません。 価格が安いので工事価格は安いのですが、耐久性が5~8年と非常に短いのが原因です。現在で最も使わ れているのはシリコン塗料になります。 最近ですと農協さんやエデンさんなどがエスケー科研とタイアップしてフッ素塗料をよく使用している感じです。ヨコイ塗装でもメインの塗料は無機塗料もしくはフッ素塗料になってきています。
ウレタン塗料は、耐候性が低く外壁塗装にはお勧めできません。そちらの根拠をまず説明したいと思います。
塗料はまず艶が引けてから、そのあと顔料が褪せてきて、 いわゆる色あせが起こる状態になります。ウレタン塗料は他の塗料と比べ比較的早く艶が引けてしまいます。 そのため現在では外壁塗装においては耐久性の低さからあまり使われる事は少なくなっております。
現在主流になっている塗料は、一般的にはシリコン塗料以上のグレードのものが多くなってきています。 日本ペイントさんシリコン塗料では「ファインシリコンフレッシュ」あたりが主流ではないでしょうか。
※ツヤびけに関して、ウレタン塗料とシリコン塗料では明らかに違いが出てきます。
ウレタン塗料のメリットとしては、塗料自体にかなり柔軟性があり雨どいや木部などの伸縮する素材に対しても対応できると言うことです。 逆にデメリットとしては上記にお伝えしたように紫外線に対して弱く、ツヤびけが早いことです。 屋根の塗装に関しては、紫外線がきついので、ほとんどウレタン塗料で塗装する事はなくなってきています。( 紫外線をからの塗膜の劣化を出るのが塗料の通夜の部分になります。)
そんな現在活躍の場を失ってきた ウレタン塗料ですが、メリットとしては非常に塗りやすく、塗膜の美観にも優れ、 どことなく高級感を感じさせるます。ヨコイ塗装で一昔前には、実際日本ペイントの「1液ファインウレタン」をよく使用をしておりました。使用する箇所としては、紫外線の当たらない車庫の内部の鉄骨、などに使用をしておりました。
逆にデメリットは、紫外線に弱く耐久性が低いと言うことになります。 したがって紫外線のよく当たる、屋根塗装においてはオススメはできません。
ただどちらにしろウレタン塗料を現在外壁で塗装使用する事はかなり少なくなってきています。
「ウレタン」は一般的に「ポリウレタン」の通称として使われており、塗料業界ではウレタンといえばポリウレタンのことを指します。ウレタン樹脂は、組成内にウレタン結合を有するポリマーのことで、基本的には2個以上のイソシアネート基をもつ化合物と2個以上の水酸基を持つ化合物を反応させることで得られます。
ウレタン樹脂塗料は、主剤として複数の水酸基を持つ樹脂(ポリオール)と硬化剤としてのポリイソシアネートを組み合わせた塗料の総称で、使用するポリオールとポリイソシアネートの組み合わせ次第で、様々な特徴を示します。
塗料としては、耐候性が求められる上塗りとしてよく用いられます。また、一液湿気硬化型の下塗りや低温硬化型塗料としても用いられます。大日本塗料株式会社より引用
ポリウレタン樹脂を使用した塗料は現在でも比較的に使われることが多いです。ウレタン塗料に比べ耐候性も高く、非常に長持ちします。 ヨコイ塗装が破風の部分に、ポリウレタンの塗料「ファイン木部用クリアー」 よく使用していますが、10年近く持っているお住まいが多いです。(破風や鼻隠し等の木部の箇所を、「キシラデコール」で塗装する事は非常に多いです。 つるっとした感じの仕上がりになるのが特徴です。「キシラデコール」単体では非常に耐候性が弱く、3年から5年に置いて塗膜が剥がれてくると言うようなことがあります。 そういった時に「キシラデコール」の上にクリア塗膜をかぶせることで、非常に耐久性を高めることができます。 ポリウレタン樹脂の塗料は鉄橋や橋などにも よく使われています。
また同様のウレタン塗料として2液型の塗料も使っておりました。 ロックペイントさんの「ユメロック」 は非常に使いやすく、また柔軟性も非常にあるため木部の塗装においても過去に非常に重宝していました。 木部の塗装事においては柔軟性をより持たせるために、弾性用の硬化剤を使うことをお勧めしております。
ウレタン塗料はシリコン塗料に比べ、とにかく安いです。したがって店舗等の塗り替えのように、5年前後を持てば充分と思うような場合で、塗り替えスパンが短い場合、ウレタン塗料を使用するのも良いと思います。 (シリコンだと7から8年程度、 フッ素塗料ですと10年前後、と言われています)
※ メーカーは机上の空論で、比較的期待対抗年数は多めに盛ってきていることがので、実際の対抗年数は2 -3年低く見積もってた方が良いです。
れている箇所としては現在使われる塗料は、フッ素と無機塗料が多いです。ベランダ床面の防水ウレタン防水に関しては現在でも使用することが多いです。
これからコールタールを塗ろうとしている人の「コールターってどうやって塗るの?」「どんな注意点があるの?」こういった疑問に答えます。
■コールターは昔と違って格段に作業性能が良くなりました。コールターと言うとコテコテで塗りにくいと言うイメージがありましたが、現在では特に希釈する必要もなく非常に塗りやすいものがメーカーから出ております。
昔は安く、防腐効果もあったので、よく使用されていました。発がん性物質があるため、現在では取り扱い業者も少なくなり、なおかつ発がん性物質を除去すると言う手間も増えたためコルター自体の価格が上がっています。
■コールターの塗装で注意をしなければいけないポイントとしましては、コールターの上にはコールターしか塗れないと言うことです。コールターの上に塗料を塗ってもコルターが、油脂を分解しコールター自体が浮き出てくるという現象が起こってきます。時間を置くと、コールターが新しくなった塗料を溶かし、まだら模様になってきます。そのため見苦しいものになってきます。
また、コールターの上にはコールターしか塗れません。その事は当然、これから素材がずっと黒色になります。したがってコールターを塗装する前には、今後その素材に色付けをする必要があるかどうかを、事前にチェックしておく必要があります。
■はけやローラーは使い捨てのものを使用しましょう。
コールターを塗装すると刷毛やローラーがいっぺんに悪くなります。そのため後から派遣などではもったいがありませんので、ホームセンターなどで売っている使い捨ての安い刷毛で塗装することをお勧めします参考:トタン屋根のメンテナンスと塗装工事
コールタールは、石炭を材料とする塗料で、昔から木や金属の錆止めを目的として使用されていました。最近では、サイディングボードの外壁やALCの外壁が増え、金属素材であるトタンはほとんど使用されなくなりましたが、コールタールの塗装が最も効果的な素材は、トタンなどの金属外壁になります。
最近ではあまり使用されない塗装ではありますが、今回は、トタンに対しては非常に効果的なコールタール塗装について、ご紹介します。
(※コールタールの上に塗料は塗ってもすぐ剥がれます。)
コールタール塗料は、他の外壁塗装で使用する樹脂を素材とする塗料とは異なり、原材料は石炭となります。コールタールは、コークスを製造する際に石炭を乾留して得られる副産物となり、黒い液体でタール臭がありますので、基本的には、塗装後の色は黒となります。コールタールには、強い防腐効果、防錆効果がありますので、金属や木材といった素材に対して、高い効果を発揮します。
特に、トタン屋根のような金属素材に対しては、樹脂製の塗料よりも高い防錆効果があるといわれています。また、コールタールには虫よけの効果もありますので、農家で使用している納屋などにもよく使われる塗料となっています。
また、この虫よけの効果は、白アリの予防にもつながりますので、建物以外にも木製のベンチやウッドデッキの見えない部分などに塗装することで、白アリの被害を防止することも可能となります。
このように、耐久性が高く、コストが安いという、非常にコストパフォーマンスに優れた塗料ではありますが、色が黒しか選択できないという点、芳香族化合物の持つ、強い臭気があるという点から、取り扱いが難しい塗料でもあります。
特に、現在はカラートタンに代表されるように、美観が非常に重要視されていることから、美観を変えることができないコールタール塗装を選ばれる方は、徐々に減ってきています。
コールタールで塗装する際にも、下地処理は重要な作業となります。特に、トタン屋根は錆が発生しやすいため、さび落としは目荒らしといった下地処理は必須になります。これらの下地処理として、さび落とし、ワイヤーブラシなどでの研磨を行うことで、さび落とし、目荒らしを同時に行うことも可能です。これらの工程を行うことで、錆や汚れが除去され、トタンがきれいになると同時に、細かな傷が入りますので塗料をしっかりと密着させることができます。
樹脂製の塗料の場合は、下塗り、中塗り、上塗りと最低でも3回の塗装を行わなければなりませんが、コールタールの塗装は、基本的には1回で仕上げることになります。もちろん、より、厚みを出すために複数回に分けて重ね塗りを行うことはありますが、基本的には1回の塗装で、ある程度の耐久性を持たせることができます。
塗装を行った後、塗料を乾燥させる必要があります。樹脂製の塗料の場合、1日程度で乾燥しますが、コールタールの場合は、速乾性の高い商品を選択したとしても、早くても1週間くらいは硬化しません。また、コールタールの場合、乾燥しても完全に固まるわけではなく、べたつき感が残るという特徴もあります。
コールタール塗料で塗装する場合、基本的には1回の塗装で仕上げることになりますので、職人さんの腕によって、仕上がりが大きく異なってしまいます。腕のいい職人さんが、丁寧に仕上げることで、重厚な黒い輝きのある塗装に仕上げることもできれば、そうではない職人さんや雑な作業によって塗りムラが目立つ仕上がりになることもありますので、コールタールで塗装を行う場合は、特に職人さんの腕が大切になります。
また、コールタールは非常に臭いがきついため、住宅の密集地で使用される場合は、ご近所さんに配慮する必要があります。特に、コールタールは気温の高い日は臭いがきつくなりがちですので、そういった日を避けて塗装するなどの配慮が必要となります。
このように、コールタール塗料は、使用方法が難しいという側面はあるものの、高い耐久性、虫よけの効果など,他の塗料では実現できないような様々なメリットも有しています。最近ではあまり使用されなくなった塗料ではありますが、トタン屋根やトタンの外壁を黒できれいに仕上げる、虫の多い農地の納屋に使用する、ウッドデッキやベンチといった木製部分を白アリから保護するために目立たない部分に塗装するなどといった使用方法もありますので、使い方によってはコールタール塗料のデメリットを最小限に抑えつつ、その効果だけを受けるといった方法も可能となります。
塗料は、そのままでは非常に使用するのが難しく、通常は少し薄めて(希釈して)使用します。この希釈によっても、耐久性能が異なってきます。
外壁塗装をしようとしている人「油性塗料か水性塗料かどちらがいいの? これから、見積もりをしたいので、外壁塗装においてよくもつ塗料の情報を知りたいです。」
こういった疑問に答えます。
なぜかというと、比較的「耐候性が高いから」です。
(弊社がよく使用するKFケミカルさん「ワールドセラ」シリーズのカタログから引用)
もちろん工事中は油性塗料は匂います。しかしながら施工後は匂いは消えてなくなり、匂いは一時的なものです。それと比べ外壁の耐候性が高くなるということは継続的なので、どちらを選ぶかという判断になります。しかし条件を変え、屋内塗装の話なら、雨や紫外線の悪条件が無いので水性塗料が、健康の面から考えてもおすすめです。
Q「水性も耐候性上がってきているって聞くけど?」
A:無理をして水性を使って耐候性が低くなるなら、油性塗料が◎
現場や営業目線の理由:塗装は天気に左右されます。ゲリラ豪雨が降れば水性塗料は、模様が流れてしまう可能性もあります。また水性塗料は油性塗料よりも安く仕入れられるので、業者さんが少しでも利幅を増やすために水性塗料を勧めている可能性もあります。施工具体例:塗膜が劣化しやすいのが、屋根、ベランダ周り、外壁、軒裏になります。したがって屋根:無機、ベランダ周り:フッ素4回塗り(下塗り込み)、外壁3回塗り(下塗り込み)、軒裏2回塗り、上記のような内容で、軒裏だけを部分的に水性を使うのも出来るかと思います。なので、油性塗料がおすすめです。
□その他の違い
外壁塗装の見積もりに質問すべき内容
結論:価格の変化を聞くことです。
なぜなら、水性塗料と油性水性塗料と油性塗料の仕入れ価格の違いを、見積もりに反映しているかどうかは、それぞれ施工業者の判断が異なるから、実際に聞いてみるのが1番良いです。
最後に、1液型と2液型という分類もあります。1液型は1つの塗料缶だけで塗料として使用することができますが、2液型は主材と硬化剤という2つの塗料缶の中身を混ぜ合わせてはじめて塗料として使用することができます。2液型は混ぜ合わせた瞬間から固まり始めるため、時間がたってしまうとカチカチに固まってしまいます。そのため、使用するごとに混ぜ合わせる必要があるため、非常に手間がかかります。その手間を削減するのが1液型塗料で、こちらは混ぜる必要がありませんので楽に使用することができますが、その分耐久性が低くます。
これらの特徴から、一般的にサイディングボードにお勧めする塗料は、2液型・弱溶剤・シリコン系の塗料となります。もちろん、一般的なおすすめとなりますので、現状や工法をしっかり確認したうえで、最適な塗料を選択する必要があります。(ただ耐久性をせっかくなので・・・と言われる方には無機をおすすめしています。)
塗料は、従前から使用されていた2液型塗料と、より手軽に使用できるよう改良がくわえられた1液型塗料の2種類があります。 2液型塗料は、塗料の主原料となる主材と、それを固めるための硬化剤の2つで構成されており、塗装を始める直前にこれら2つを混ぜ合わせることによって塗料として使用できるようになります。
2液型塗料は、硬化剤を混ぜた後、すぐに使用しなければ、塗料がどんどん固まってしまい、使い物にならなくなるというデメリットや、硬化剤を混ぜ合わせる手間がかかるといったデメリットがある一方で、耐久性に優れており、塗装できる素材も比較的広範囲にわたります。
一方、1液型塗料は、時間経過とともに自然と固まる塗料であるため、水やシンナーで薄めるだけですぐに使用することができます。一方で、2液型塗料と比べると、耐久性の低さや塗装できる素材の範囲で劣っている塗料となっています。
2液型塗料は、硬化剤と混ぜ合わせるとすぐに使用しなければならないと言われていますが、実際に使える時間はどの程度なのでしょうか。その時間は、商品によって異なりますが、3時間~10時間となっており、日をまたいで使用することはできません。特に夏場の高温時はすぐに固まってしまいます。
2液型塗料では、コンクリートやモルタル、サイディングボードといった1液型塗料でも塗装できる素材に加え、ALCパネルやスレート板、鉄部、亜鉛メッキ鋼、にも塗装することができますので、非常に広範囲の素材に使用することができます。
一般的に、2液型塗料の耐用年数は、1液型塗料の耐用年数よりも3年程度長いといわれています。ただし、この耐用年数は塗料メーカーが公表している数値ではなく、現場の職人さんの感覚ですので、その期間は多少前後します。
1液型塗料では、硬化剤がすでに混ぜ込まれていますのが、2液型塗料では職人さんの配分で硬化剤を混ぜ合わせる必要があります。この作業自体は、少しに手間がかかるものですが、自分で硬化剤を混ぜ合わせることができる2液型塗料では、硬化剤の種類を選択できるというメリットもあります。
その選択肢の1つが「弾性硬化剤」といわれる特殊な硬化剤を使用できるという点です。一般的な硬化剤を使用した塗料は、塗装した部分が強力に硬化することによって、強い塗膜を貼り、防水性能を高めています。一方、弾性硬化剤を使用した塗料は、その名の通り弾力性が非常に強い塗料となります。弾力性が強い塗料ということは、塗装した部分が強力に硬化するのではなく、環境によって伸縮するゴムのような塗料ということです。
サイディングボードのような動きのない外壁素材に塗装する場合は、塗料がしっかりと固まった方が、高い耐久性を有することができますが、樋や木材といった温度によって伸縮する素材に塗装する際には、硬化してしまう塗料の場合は動きに耐え切れず、塗膜にひびが入る原因となります。
一方、弾性硬化剤を使用した塗料を使用した場合、温度によって樋や木材と一緒に塗膜自体が伸縮しますので、ひびが入る心配がありません。そのため、塗装する外壁によって、弾性硬化剤を使用することができる2液型塗料は、手間がかかる分、耐久性に優れた塗料といわれています。

メリットが多いように見える弾性硬化剤にもデメリットは存在します。 1つは、窯業系サイディングボードには使用できないという点です。窯業系サイディングボードは、断熱材は含まれており、表面が80度近い高温になってしまいます。
弾性硬化剤を使用すると、温度によって伸縮してしまいますので、80度もの高温になってしまうと、外壁以上に膨張し塗膜が痛む危険性があります。そうなると、見た目も悪くなるほか、膨れた部分の耐久性能が著しく低下していますので、耐久性能にも問題が生じてしまいます。
また、塗膜自体が伸縮する関係上、どうしても硬化する塗料に比べると耐用年数が低くなってしまいます。そのため、塗装する場所を適切に選択しなければなりません。
外壁塗装は通常7年~10年という期間で定期的に実施すべき建物のメンテナンスです。定期的に外壁塗装を実施しなければ、外壁に塗った塗料の膜(塗膜)が徐々に薄れ、塗膜によって保護していた紫外線や湿気の影響を外壁そのものが受けてしまうことによって、外壁材の腐食や建物内部に雨水などが吸収されることによって、建物内部の腐敗につながってしまい、建物耐久年数そのものが下がってしまうことになります。
そんな大切な外壁塗装ですが、その費用は1回数十万円~百万円以上と高額になります。そのため、1回外壁塗装を行った後は、できるだけ長持ちさせたいと思います。
外壁塗装の状態を維持するためには、その外壁塗装を依頼するときにもやっておかなければならないことがあります。それは、
の3点になります。
塗料には、大きく分類するとアクリル系塗料、ウレタン系塗料、シリコン系塗料、フッ素系塗料、無機という5種類があります。この塗料の種類によって、耐久性は大きく異なり、全く同じ環境、同じ場所、同じ塗装方法で使用した場合、
の耐久度があるとされています。(実際は、もっと短く感じます。)
その分、価格もアクリル系塗料が最も安価で、フッ素系塗料が最も高価となりますが、例えば、60年間同じ建物を使い続けると考えた場合、アクリル系塗料の場合は10回~12回程度、フッ素系塗料の場合は3回~4回と外壁塗装の回数が大きく異なります。そのため、1回あたりのコストを高くしても、長期間使える塗料を塗っておいたほうがお得ということもあり得ますので、この点をしっかり検討する必要があります。
海に近い地域や台風が多い地域と、晴れた日が多い地域ですと、紫外線の量や湿気の量が大きく異なります。また、外壁の方角や、隣家との距離、日当たりなどによっても、建物の受けるダメージが異なりますので、その立地や環境に合わせた塗装を行うことが塗装を長持ちさせる条件となります。
例えば、屋根や日当たりのいい南側の外壁は劣化が早いため、無機系塗料を使用する、塗装を厚くしておくといった工事を行っておけば、塗装を長持ちさせることができます。
外壁塗装は、最低でも下塗り・中塗り・上塗りという3回実施します。この3回の塗装が非常に重要で、これより回数が少ない場合、耐久性は大きく低下することとなります。
悪徳業者は、安価に依頼を受ける代わりに、塗装の回数を減らすことによってコストダウンしていることが多々あり、下塗りと上塗りの2回、上塗りだけの1回という業者もあるようです。(塗装の耐久性は、塗膜の厚みにも密接に関係しています。)
そのため、塗装を3回行わないような業者には、依頼すべきではありません。なお、塗装は最低でも3回必要ということですので、状況に応じて下塗りや中塗り、上塗りの回数を増やすことに問題はありません。塗装の回数が増えれば、それだけ塗膜が厚くなりますので、耐久性が向上することになります。(ただ過度に厚く塗りすぎると、剥がれの原因になることもあります。)そのため、塗装の回数を増やす提案をしてくる業者は、それだけ耐久性の向上を考えている業者ともいえます。
アクリル系塗料は、モルタル外壁のひび割れに効果的な塗料でしたが、耐久性が6年から8年と低く、汚れも付きやすいという欠点があります。価格そのものは安いのですが、これらの欠点から、長期的に見た場合、頻繁にメンテナンスしなければならないことから、トータルとしては他の塗料よりも高額となってしまいます。また、これらの欠点のために、高耐久性が求められる屋根用の塗料としては、現在、アクリル系塗料はほとんど出回っていないという状況にあります。
ウレタン系塗料は、比較的安価で塗料の素材が柔らかく、細部の塗装に適した塗料と言えます。しかし、近年主流となっているシリコン系塗料と比べると、耐用年数が7年~10年とやや短く、シリコン系塗料の価格低下から、選択される頻度は減少傾向にあります。ウレタン系塗料は、万能塗料として、どの部分にも塗れるため、場所によって塗料を使い分けることを嫌う業者では、今でもメインで使っているケースもあります。
なぜかというと、何故かと言うと紫外線に弱く、耐久性が低いからです。せっかくの足場を作っての大掛かりな工事は、なるべくスパンを長く、より持たせたいという考えからです。実際の体感としては6、 7年で色あせが見られているような感じを受けます。日当たりがよく紫外線が強い塗膜環境に悪いような箇所では、5年程度で色あせが始まってくると思います。元請け業者さんから下請けの施工業者さんに「とりあえずウレタン塗料で塗っておけばいいんじゃない。」と言うような会話はよくある話です。
ダメと言うわけではありません。外壁の塗料としてはお勧めしておりません。ウレタン塗料は特に柔軟性に優れております。したがって木部の塗装や雨どいの塗装によく使われております。特に破風の塗装においては、浸透性の塗料(キシラデコールなど)は塗膜も薄く紫外線によってすぐ劣化してしまいます。それらの耐久性を高めるために、キシラデコールの上に木部用ウレタンクリアーを塗って耐久性を持たせるようなことをしております。上記の木部用クリアーはポリウレタンの塗料で耐久性も良いです。
ウレタン系でも、アクリルウレタンよりポリウレタンのほうが、断然紫外線に強く耐久性があります。
塗装業者では、緑木部や雨どいにウレタン塗料を使用すると思います。その理由としましては、ウレタン塗料に柔軟性があるからです。木や雨どいは性質上夏冬で伸び縮みが外壁と比べ大きいです。そのため業者はより柔軟性の高い塗料としてウレタン塗料を採用しています。(ヨコイ塗装では、外壁のグレードに合わせて、上記箇所もフッ素系塗料の弾性用硬化剤を使用することで塗装をしています。)
外壁塗装の見積もりに質問すべき内容「外壁と木部や雨樋の耐久性は一緒ですか?」もし木部の浸透性塗料の使用の記載があったら、「何年ぐらいもちそうですか?」と聞いてみてくださいね。
ヨコイ塗装では、まずウレタン塗料は耐久性がないので使用しません。使っても破風だけです。キシラデコールなどの浸透性の塗料の上に保護膜を作るためにクリア塗料を塗るだけです。そしてなおかつその塗料はポリウレタン系が良いと思います。
参考して、見積もり時には、外壁材にどれぐらいの耐久性がある塗料を提案されているかを把握することです。そしてそれに伴い、雨どいや木部の塗料の耐久性も把握することです。せっかく外壁材に良い塗料を使っても、雨戸や木部がグレードが低くてすぐ色あせをして、見苦しくなったらもったいないですよね。もし雨樋が歪みなど生じていて古くなっているとしたら、その際無機やフッ素など良い塗料を外壁に使用するならば、予算があるようでしたら、雨どいはいっそのこと交換しても良いと思います。
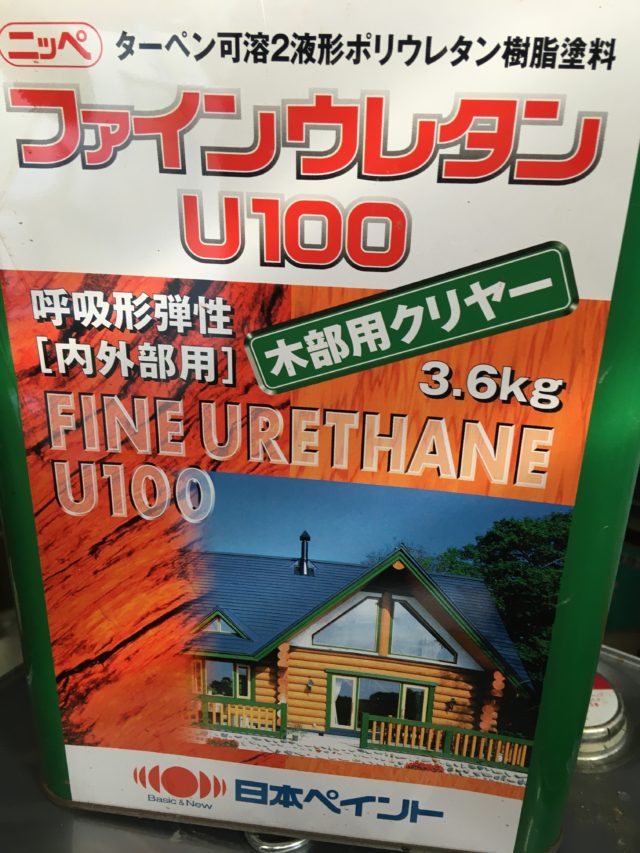
シリコン系塗料は、最近まで最もよく使われている塗料になります。耐用年数は12年~15年と比較的長く、シリコンの性質から汚れにくさと高耐久性を両立させることができると言われています。ただ実際使用してみると南側など条件の悪いところや塗料の種類によっては、10年も持たない場合が見られます。
シリコン系塗料にお勧めの外壁は、モルタル、ヘーベル(主に水性セラミシリコンがおすすめ)、サイディング(クリーンマイルドシリコンがおすすめ)、ジョリパット(アートフレッシュが条件付きでおすすめ)と、様々な外壁で利用することができることも特徴の一つです。
2015年に発売されたばかりの新しい塗料です。ラジカル系塗料が発売されるまでは、シリコン系塗料が最もよく利用されていましたが、ラジカル系塗料発売以後、現在においては、ラジカル系塗料がよく利用されています。
ラジカル系塗料では、シリコン系塗料までで防ぐことができなかったUVや酸素、水による塗膜の劣化を防止することができます。そのため、耐用年数は14年~16年とシリコン系塗料よりも耐久性が上がっています。価格もほとんどシリコン系塗料と同じで、かつ、高額なフッ素系塗料に似た効果があるため、シリコン系塗料に変わる人気No.1の塗料となっています。ただまだ年数が経過後の実績には不安があります。
現在販売されている中で、最も高額な塗料がフッ素系塗料です。一般的には、フッ素系塗料が一般家庭用として使われている例はあまりなく、商業施設向けの塗料と考えられていますが、非常に耐久性が高いため、予算に余裕があれば、検討の価値はあると思います。フッ素系塗料は、その名のとおり、主成分がフッ素となっており、耐久年数は8年から15年と非常に長いとされています。
フッ素系塗料が高額であることを逆手にとって、訪問販売等において、最初にこの塗料で見積もりを行い、外壁塗装は高いというイメージをつけておいて、ラジカル系塗料やシリコン系塗料(もしくはウレタン系塗料)での見積もりを作成し、通常価格を「安い」と思い込ませる方法も使われていることもありますので、フッ素系塗料は高額であるという点だけは、最低限、覚えておいて損はないでしょう。どの程度価格が変わるかというと、坪単価で、フッ素系塗料とラジカル系塗料では5万円前後異なると言われています。そのため、30坪程度の家の場合、塗料だけで150万円程度の違いが生じてしまいます。しかし、その効能は非常に優れており、スカイツリーにも使用された実績のある塗料となっています。
このように、塗料によって耐久年数や性能、価格に大きな違いがあります。ご自宅の外壁を塗装する場合は、フッ素塗料を利用されることを強くおすすめいたします。塗り替えスパンが短くなりますので、お住いのトータル的なメンテナンス費用を抑えることができます。外壁塗装の見積書を取得する際に、使用する塗料についても記載があるかと思いますが、商品名で記載されている場合や記載がない場合は、どの塗料を使用するのか、きちんと確認しておくことが重要です。
また、シリコン系塗料とされていても、単層弾性シリコン(セラミックシリコン)については、工程短縮用の塗料であるため、耐久年数が低く外壁塗装工事には不向きな塗料とされていますので、この点にも注意が必要です。
今回の現場では、日本ペイントさんの「ファイン4Fセラミック」を使っています。こちらの塗料はフッ素系の塗料であります。一般的にフッ素系の塗料は硬いイメージがあるのですが、この塗料はその中でも柔軟性に富み、なかなか塗りやすいものです。
また実績としましても、ヨコイ塗装の塗装後5年以上経過したOBのお客様の外壁を見ても、まだまだ艶が十分にあります。色あせた現場にはまだ出くわしていないです。実績として時間経過的にもかなり優れた成果を出している塗料です。フッ素系の塗料ですと、特徴は紫外線に強いと言うことで、かなり耐久性もいいです。したがってヨコイ塗装では、外壁塗装工事においてかなりおすすめしています。塗装は、せっかく足場も作って経費がそれなりにかかかりますので、「ファイン4Fセラミック」若干金額がかさみますが、コストパフォーマンスで考えるとかなり良いのです。
ただ、こちらの塗料が1缶あたり大体5万円以上します。塗料としても結構高いのです。このためコストを下げるために、シンナーで薄めて、なるべく少ない量で塗ろうとする業者さんもいます。(塗膜が薄くなり、耐久性が落ちてしまいます。)やっぱり長持ちさせるためにも、なるべくローラーでたっぷりと塗膜に厚みがつくように塗料を塗ってもらうと良いと思います。適切な品質の塗装工事をしてもらうためにも、ぜひ使用した塗料の缶の数を確認してみてください。
フッ素系塗料よりも性能の高い無機系塗料は、1㎡あたり4,500円~5,500円と非常に高額ですが、その分耐久性能も12~25年と非常に長くなっています。
そもそも、無機塗料の「無機」とは一体何なのでしょうか。ここでいう「無機」とは、有機物の対義語である無機物のことを指しています。つまり、ガラスや陶器と同じといえます。ガラスや陶器は、時間とともに劣化するということがありませんので、耐久性に優れているといえます。逆に有機物とは、植物やプラスチックのように、時間とともに劣化するもののことを言います。
では、無機塗料という名前であるからには、塗料の成分はすべてがガラスや陶器と同じ無機物でできているのかと言われると、そうではありません。すべてが無機物ですと、確かに半永久的に性能を保持し続ける塗料となりますが、無機物だけですと、塗料に必要な弾力性や接着性が作り出せませんので、塗料として使用することはできません。あくまで樹脂中に含まれる無機成分が30%程度のものを無機塗料としています。
実際に無機塗料を塗った塗膜は、樹脂中に含まれるアクリル成分によって無機成分が連結されているという構造になります。
無機塗料は、100%でないにしろ、成分の中に無機物が含まれていますので、その無機物部分については、ほとんど劣化することはありません。そのため、通常の有機物のみで作られている塗料に比べて、高い耐久性能を誇ります。特に、色あせやチョーキングといった塗装の劣化を代表する現象は、有機物である顔料によって発生するため、無機塗料では非常に発生しにくくなっています。さらに、有機物を栄養素とするカビや藻についても、その栄養素である有機物が限りなく低いため、発生しにくくなっています。
しかし、デメリットとして、ひび割れが発生しやすいという特徴もあります。無機物そのものは、非常に硬い素材ですので、樹脂中の無機物が多くなればなるほど、ひび割れが発生しやすくなります。しかし、無機塗料が塗料として販売されている以上は、外壁塗装のプロである職人さんが、しっかりと施工方法を守って塗装すれば、ひび割れが発生することはほとんどありません。そのため、価格面でも施工面でも、DIYに向かない塗料だといえます。
無機塗料で塗装した場合、耐久性能は20年~25年程度と説明しましたが、それだけの長期間、外壁塗装をしないとなると、外壁の汚れが非常に気になるかと思います。そもそも外壁塗装は、建物のメンテナンスという側面の他に、建物の美観を向上させるという目的もありますが、最長で25年もの間、塗装を行わないとなると、しっかり掃除しておかないと見た目が悪いのではないかと心配される方も多いのではないでしょうか。
しかし、無機塗料は、汚れが付きにくいという特徴もあります。多くの無機塗料に含まれる成分には、親水性が非常に高くなっています。親水性が高いというのは、水と非常になじむという性質のことを指します。無機塗料が水となじむとどうなるかというと、塗料と水が密着しやすくなりますので、塗料の上に汚れがついていたとしても、その間に水がはいりこみ、汚れを流れ落とすことができるのです。
つまり、無機塗料をつかうことで、雨や軽く水で流すだけで、簡単に汚れを落とすことができるのです。イメージとしては、車のガラスコーティングと同じような特徴といえます。
また、無機塗料には静電気が発生しにくいという特徴もあります。
外壁の汚れには、泥はねなどの直接的な汚れの他に、ほこりや小さなごみが付着することで発生する汚れもあります。それらは、静電気によって付着しますが、静電気の発生しにくい無機塗料では、これらの汚れも有機塗料に比べると付着しにくくなっています。
住宅を購入する際や、外壁塗装を行う際に、業者から「この外壁は、今後30年間は塗装しなくても大丈夫です」というセールストークを聞いたという方が、少なからずいらっしゃいます。この業者の30年間というのは、どの程度の信ぴょう性があるのでしょうか。
一部の塗装業者のセールストークとして「今回、30年間塗り替えなくてもいい塗料で塗装します。」というものがあります。はたして、本当に30年間持つ塗料というのは存在するのでしょうか。
結論から先に申し上げますと、2018年現在、30年間持つ塗料というのは分かりません。塗料の耐用年数は、塗料に配合されている樹脂によって大きく異なります。例えばアクリル塗料の場合、コストが安い分、耐用年数は6年~7年と非常に短くなっています。耐用年数が短い順に並べると、アクリル塗料(6年~7年)、ウレタン塗料(8年~10年)、シリコン塗料(10年~13年)、フッ素塗料(15年~20年)となります。ほかにも、断熱塗料、遮熱塗料、光触媒塗料なども存在しますが、いずれも最大で20年程度の耐用年数となっています。そのため、繰り返しになりますが、現時点で耐用年数が30年を超える超えるかどうかはわかりません。
では、「30年間塗り替えなくていい塗料で塗装する」と説明していた業者は、全くのでたらめをセールストークとしているのでしょうか。その答えは、半分は正解ですが、もう半分は不正解と言えます。なぜなら、そういった業者の手口としては、「自社開発の塗料」として、30年以上の耐用年数を有する塗料を勧めてくるためです。自社開発の塗料であれば、「自社の基準で」計測したデータに基づいて、耐用年数30年を算出することができますので、そういう意味では嘘のセールストークとは言えないのです。
しかし、資金力が豊富な大手塗料メーカーが、長期間研究を重ねてきて未だ実現していない30年以上の耐用年数を有する塗料を、研究設備の整っていない塗装業者が、自社開発で作成できるほど簡単ではありません。実際に、30年以上持つというセールストークを信用した方の中で、10年以内に塗装工事を再度実施したという方も多数いらっしゃいます。
では、仮に30年の耐用年数を有する塗料が、今後開発された場合には、本当に30年間、塗装工事を行う必要はないのでしょうか。残念ながら、その答えは「否」となります。
塗装工事を行う際には、その下地処理として、外壁や屋根、その他建物を構成するあらゆる部分に対して、補修作業を実施しています。この補修は、塗装が古くなったことによる雨水の侵入に起因するものの他、経年劣化等による補修も含まれています。
例えば、屋根に設置されている雨どい等は、定期的にメンテナンスを行わなければ、雨どいが詰まったり、経年劣化による歪みで傾斜が無くなってしまったりという原因で、雨水をうまく地上に流すことができなくなることもあります。こういった補修作業を全く行わずに30年間、建物を持たせることは、非常に難しく、外壁そのものに問題はでなくても、ほかの部分から建物全体にダメージを受けてしまう可能性があります。
こちらは、新築時によく聞く説明として「この外壁はメンテナンスフリーですので外壁塗装の必要はありません」というものです。こちらも、実際には誤った内容と言えます。ここでいう「メンテナンスフリー」というのは、あくまでハウスメーカーが机上で算出したデータに基づくもので、それを信じて外壁塗装を行わなかった場合、外壁塗装を行った場合と比べて、建物の耐久年数は大きく低下します。また、「2.30年塗装が実現した場合の問題点」でも説明した通り、雨どいやサッシといった、外壁以外の部分が先に劣化してしまい、その部分の補修が行えないために、そこから建物全体への深刻なダメージが伝わってしまう可能性があります。
外壁塗装は、1回あたりの料金が高額ですので、できる限り少なくし、出費を抑えたいところでしょう。そういった中、30年間、外壁塗装を行わなくてよいという言葉は、非常に魅力的に聞こえるかもしれません。これまで、10年に1回、100万円の外壁塗装を行っていたとしたら、30年間で300万円の出費となるところ、「少し高いですが…」と、200万円の工事費用で30年持つといわれると、30年持つという塗料を試してみたくなってしまうかと思います。
しかし、これまでご説明した通り、30年間の耐用年数を有する塗料は、まだ実績が出ていません。必ず、おそらく30年以内に再度塗装工事が必要となります。そうみると、本当に、そのコストは有意義なものなのでしょうか。
トイは、屋根の雨水を地面に流す役割のある付帯部分です。トイがなければ屋根から雨水が外壁を伝って流れ落ちるため、外壁内部に雨水が浸入する可能性が高まり、外壁内部を腐食させる可能性が高まりますので、非常に重要な部分になります。
トイが、その機能を果たせなくなる一番多い原因は、落ち葉などによる「詰まり」となります。この詰まりは、塗装や補強によって詰まりにくくするということは行えませんので、年に1回程度、ご自身で点検していただき、詰まりがあれば早めに解消していただくことになります。
次に、トイの傾斜や破損についてですが、トイは屋根や外壁材と比べると、破損しやすい素材になっていますので、強い風や雪などによって、不自然な傾斜ついてしまったり、破損してしまうということがあります。
台風のように、とても強い風で、大きく破損してしまった場合は、すぐに補修する必要がありますが、見た目ではなかなか分かりにくい斜頸や破損もありますので、そういった場合は外壁塗装の際に、しっかりと補修しておく必要があります。
他にも、屋外で使用していることによって、太陽光や温度変化による経年劣化も生じてきます。経年劣化によって、明らかな破損等がなければ、外壁塗装などのメンテナンス時に、併せて補修や交換を行い、耐久性能を回復させる必要があります。
鼻隠しは、トイを取り付けるための下地となる役割をもった板材で、トイの裏側にあります。また、屋根の構造材を隠す役割ももっており、こちらもトイと同じく、重要な付帯部分となります。
鼻隠しは、現在では木材以外の素材も使用されていますが、10年以上前の建物ですと、ほとんどの建物で木材が使用されていますので、雨水や経年劣化によって、その耐久性能が下がってきてしまいます。鼻隠しは、トイの下地となっていますので、鼻隠しが劣化してしまうと、トイそのものが正しく機能しなくなる可能性が高くなります。そのため、鼻隠しも定期的なメンテナンスが必要となります。

建物には、他にも破風板や幕板など、様々な付帯部分が存在します。それらの付帯部分は、デザイン性のみでつけられている者はほとんどなく、いずれも建物を保護するために重要な役割を担っています。それらの付帯部分についても、屋外で使用している以上は、屋根や外壁材と同様に、太陽光や風雨、温度変化などによる劣化が少なからず生じてしまいます。
これらの劣化を放置してしまうと、建物を保護する機能が損なわれてしまい、建物全体に深刻なダメージが生じてしまう可能性がありますので、付帯部分についても定期的なメンテナンスが必要となります。
多くの方は、屋根や外壁の塗装工事を行う際に、併せてトイのメンテンナンスや鼻隠しの塗装などを実施されるのではないでしょうか。ご自身の判断で塗装工事に合わせてメンテンナンスを依頼している方もいらっしゃれば、塗装業者に言われるがままに、メンテンナンスを依頼している方もいらっしゃるかと思いますが、塗装工事に合わせてメンテンナンスを行うことで、様々なメリットがあります。
まず、塗装工事を行うことで、屋根や外壁の耐候性が向上しますが、この時にトイや鼻隠しの補修や塗装を行わなかった場合、屋根や外壁の耐候性と付帯部分の耐候性に差が生じてしまいます。外壁塗装はおよそ7年~10年ごとに実施しますので、比較的長期間、この差が残ってしまうことになります。年数がたつほど、この耐候性の差が大きくなり、やがて、屋根や外壁には一切問題がないにも関わらず、付帯部分の劣化から屋根や外壁材の内部から腐食が進行してしまうということもあります。
この現象を防止するためには、付帯部分が劣化する前に補修や塗装を行う必要があるのですが、次回の塗装工事までは持ちませんので、2~3年後に付帯部分のみの補修や塗装を行う必要が生じてしまいます。そうなると、外壁の塗装工事では若干の節約ができたとしても、付帯部分の塗装工事で再度、職人さんの確保や足場の作成、養生といった作業を行う必要が生じてしまいますので、1回の塗装工事ですべて実施するよりも割高な料金がかかってしまいます。
また、次回以降も外壁の塗装時点では付帯部分は劣化しておらず、また別の時期に劣化が生じるといったように、継続して時期をずらして工事を行わなければならなくなります。
そのため、屋根や外壁と付帯部分は、耐候性を合わせて塗装工事するのがおすすめの方法となります。
弾性塗料とは、基本的には2液型の塗料を使用し、主剤に硬化剤で弾性を持たせた塗料のことを言います。また、現在では、1液型でも弾性を持たせた弾性塗料も登場しており、選択肢が徐々に拡張されています。 塗料は、その弾性の強さ(塗料の硬さ)によって、硬質塗料、微弾性塗料、弾性塗料の3段階に分類することができます。
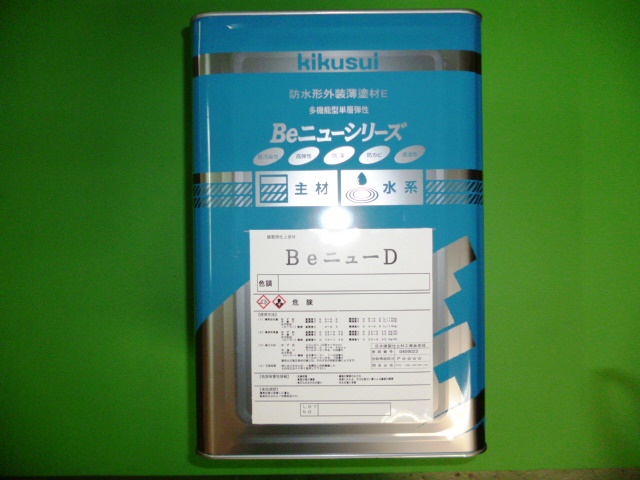
弾性塗料を使用した塗装には、単層弾性と複層弾性という2種類の工法が存在します。
単層弾性は、弾力性の高い塗料を上塗りに使用するという工法で、少ない工程で弾性塗料を使用することができる工法となっています。しかし、弾性塗料を上塗りでしか使用していない分、弾性に影響を与える紫外線を直接受けてしまうこととなり、長期間の弾性の維持には向かない工法となります。また、本来は厚く塗装しなければならない弾性塗料ですが、ローラーを使用して通常の塗装と同じように塗ることも可能であるため、業者や職人によっては、期待通りの防水性能を発揮できないという問題点も存在します。
複層弾性は、弾力性の高い下塗り塗料もしくは中塗り塗料を使用して下塗りや中塗りを行い、上塗りは他の塗料を使用する工法となります。この方法ですと、上塗り塗料によって紫外線に弱い弾性塗料を隠すことができますので、弾性を維持しやすくなります。
ただし、単層弾性の場合、下塗り1回、上塗り2回の計3回の工程で塗装工事が完了するのに対し、複層弾性の場合は下塗り1回、中塗り2回、上塗り2回と、計5回の工程が必要となるため、塗装の期間や使用する塗料の量が増加し、コストアップしてしまうというデメリットも存在します。
弾性塗料は、高い防水性能を有していますが、その反面、外壁そのものの熱や水分の影響を受けやすいという特徴もあります。そのため、蓄熱性が高いサイディングやALCに使用することはできません。これらの外壁材に弾性塗料を使用した場合、外壁材の温度が上昇し、弾性塗料がその熱によって膨張してしまうことになります。また、コーキングなどが劣化していた場合、そこから水分が中に侵入してしまうことになりますが、防水性能が高いため、入り込んだ水分が外に出られなくなり、外壁材と塗料の間に停滞してしまうことによって外壁材そのものが傷んでしまうこともあります。さらに、弾性塗料の伸縮だけでは、コーキング部分の動きに追従することができませんので、コーキングの上から塗装を行ったとしても、短期間で追従できない部分から塗装が剥がれてしまうことにもつながります。
そのため、弾性塗料は、サイディングやALC、軽量モルタルといった熱をためやすい外壁材、コーキングによって外壁材同士を接続している外壁材に使用することができません。弾性塗料は、高い防水性能を有する塗料で、使い方によっては非常に効果のある塗料となります。しかし、その特徴をしっかり理解し、使用する外壁材や環境に応じて厚みや工法を調整するなど、その効果を最大限に発揮するためには、十分な知識と経験を有していなければならない、取り扱いの難しい塗料であるともいえます。そのため、弾性塗料を使用して塗装工事を行う場合は、知識・経験を有した業者、職人に依頼する必要があります。
塗料で気にするポイントといえば、アクリル塗料やシリコン塗料といった樹脂の違いではないでしょうか。樹脂が異なれば、耐候性や耐久年数、価格が大きく異なりますので、この選択は慎重になる方が多いと思います。
しかし、例えば「シリコン塗料」を選択した場合に、数あるシリコン塗料の中から、「この塗料がいい」というところまで気にされている方はほとんどいらっしゃらないのではないでしょうか。もちろん、非常に多く販売されている塗料の中で、お客様ご自身で塗料を選択するというのは、無理があるかと思います。しかしながら、業者が使用するとした塗料が、実は低品質の塗料かもしれません。
実は、一部の悪徳業者では、自社開発したとする非常に質の悪い塗料を使用して利益を得るといった手法が用いられています。塗装業者が片手間に開発した塗料が、塗料メーカーが、塗料を専門に研究・開発した塗料よりも高品質であるはずがありません。そのため、塗装業者が「自社で開発したオリジナルの塗料」を勧めてきた場合、その業者に依頼するのは、少し様子を見てみたほうがいいかもしれません。
塗料に求められる品質は、耐候性・耐久性能が優れていることが挙げられます。同じシリコン塗料であっても、質の悪い塗料を使用した場合と、高品質な塗料を使用した場合とでは、耐久年数が数年違ってくることもあります。また、塗料の色合いも重視する品質となります。高い品質を有する塗料は、紫外線等による劣化で色褪せが発生したとしても、緩やかな変化で気付きにくいのですが、質の悪い塗料ですと、色褪せの速度が速く、気付いたら全く違う色になっていたというケースや、色褪せにムラがあり、見た目が非常に悪くなってしまうといったケースも発生します。
塗料は、塗装業者が開発したという塗料より、塗料メーカーが開発した塗料のほうが高品質であるというご説明はすでに行った通りですが、塗料メーカーが開発した塗料であれば、すべて高品質なのかと言われると、そうではありません。塗料メーカーは、塗装する目的に合わせて最適となる塗料を選択できるよう、様々な種類の塗料を開発しています。中には、品質はワンランクかツーランク下がっても、価格が安い塗料で塗装を行いたいというニーズにこたえるため、品質を犠牲にして低価格化している塗料も存在します(それでも、塗装業者が開発したという塗料よりは品質的には安心できます)。
そのため、「有名な塗料メーカーが販売している塗料だから、安心」という考えで塗料を選択してしまうと、想像していたよりも品質が高くない高価な塗料を使用してしまうというケースもあり得ます。塗料を選択する場合には、ブランド名だけでなく、塗料そのものの品質を確認するようにしなければなりません。

塗料を選択する場合は、ブランド名や塗料そのものの品質のほかに注意しなければならない点があります。それは、塗料の使用用途です。
塗料メーカー各社は、塗装する目的に合わせた塗料を開発しています。例えば、木部を塗装するのに最適な塗料を鉄部に使用した場合、いくら高品質な塗料であったとしても、本来の性能を発揮することができません。「何を当たり前な…」と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、悪徳業者やDIYで、塗装部分に合わせて塗料を変更せず、すべて同じ塗料で塗装しているというケースを多く目にします。もちろん、同じ塗料ですべての部分を塗装してしまえば、コストは低く抑えることが可能です。
しかし、その場合、いくら高品質な塗料を使用したとしても、残念ながら、その恩恵を受けることはできなくなります。
塗料は、どうしてもアクリル塗料やシリコン塗料、フッ素塗料とった樹脂に目を奪われがちになってしまいます。もちろん、それらの要素が、外壁塗装の耐久性能や価格を左右するため、よく検討していただく必要がありますが、それらの樹脂の中から、いずれかを選択したのちにも、様々な塗料の選択が可能であるということ、また、その塗料選びが非常に重要であるという点をご認識いただきたいと思います。
塗料は、密閉した缶で販売されていることが多く、缶詰などのイメージから、未開封であれば消費期限は無いと勘違いしている方がいらっしゃるようですが、未開封であっても消費期限は存在します。メーカーや塗料によって、この消費期限は様々に設定されていますが、少なくとも、「消費期限のない塗料」は存在していません。その期限の長短はあっても、必ず塗料に消費期限は定められています。
この記事を記載するにあたり、塗料の消費期限がどの程度周知されているのか、調査してみましたが、「塗料の粘度が増して、濡れなくならない限り問題ない」といった説明をされているところが何か所かありました。あくまで、その説明は、「塗装に品質を求めず、塗れればいい」という前提に立てば、問題ないのかもしれません。しかし、塗装をする目的は、屋根や外壁に水分などが侵入して建物にダメージを与えないために行うのであって、ただ塗ればそれで目的が達成できるわけではありません。塗装を行う目的を達するのであれば、品質が保証されている消費期限が切れていない塗料(さらに、できるだけ新しい塗料)を使用する必要があるのです。

塗料に未開封の場合の消費期限は明記されていますが、開封した後の消費期限は明記されていません。これは、その保管状況等によって期限が異なるため記載できないというわけではなく、塗料は一度開封したものについては、その塗装工事のタイミングで使用しなければ、本来の品質を維持できないためなのです。塗料は、空気に触れることで酸化が進みますが、酸化した塗料は本来の性能を発揮することができなくなります。そのため、一度開封した塗料は、基本的には使い切りと考えなければなりません。
なお、開封済みの塗料を保管した場合、皮張りや粘稠化といった症状が発生します。皮張りとは、塗料の表面が乾燥することで薄い膜が貼る症状のことで、この膜となった部分は使用することができません。粘稠化とは、塗料の粘度が増すことを言い、そのまま放置することで、塗料がゼリー状に固まってしまいます。もちろん、こういった症状が発生した場合も、その塗料を使用することができません。
つまり、一度開封した塗料というのは、品質が低下するだけではなく、皮張りや粘稠化といった症状で、塗料そのものが使用できなくなる可能性も高いのです。
この消費期限というのは、塗料を製造しているメーカーが「塗料の品質を保証する」期限であり、言い換えれば、この期限を過ぎた塗料は、メーカーが公表している通りの品質を出すことができない可能性が高い塗料と言えます。つまり、使用期限が1年と定められている塗料を購入し、2年間使用せずに放置していた塗料を使用した場合、塗装工事の品質は著しく低下する可能性が高く、本来であれば7年~10年程度は耐用年数を有する塗料であっても、わずか数年で塗膜にひびがはいったり、塗装が剥げてしまったりすることがあります。
しかし、これを承知で、使用期限が切れた塗料であっても使用する業者が存在しています。塗料を事前に大量購入することによって、その仕入れ価格を大幅に下げておき、消費期限を過ぎても使用できなかった在庫について、そのまま破棄するのではなく、使用し続けるという業者がそれにあたり、塗装工事の品質については2の次で、自社の利益を最優先で考えている、所謂、悪徳業者と呼ばれる業者です。業界では、別の塗装工事で残った塗料を保管しておき、再利用するというのはよくあります。しかし一度開封した塗料は、空気と触れ合うことで、品質は徐々に低下していきます。そのため、塗装工事を依頼する場合は、そういった消費期限切れの塗料や、開封済みの塗料の利用状況をよく選定する必要があります。特に下塗り材は、上塗り塗料もろとも剥がれる危険性が出てきますので、要注意です。
また、一部の業者では、塗装工事の単価を下げる際に、「古い塗料を使用してもいいか」と確認してくることがあります。これは、上記の悪徳業者のケースとは異なり、お客様の意思確認を行っている分、優良な業者であるといえます。しかし、その場合でも、消費期限内であることは確認しなければなりません。いくら工事費用が安くなったとしても、消費期限が切れた塗料を使用しては意味がありません。

塗料の基本的な使用方法は消費者庁の定めにより、製品の品質に応じて、以下の項目を表示するよう定めています。
①については、もっとも基本的な事項で、下地処理をしっかりと実施しなければならないことを示しています。この項目については、塗装後の塗料の品質を維持するための項目となっています。
②については、後半部分の「塗料を底から十分にかき混ぜる」という点が非常に重要です。このかき混ぜが足りなければ、塗料の色のムラや塗装した際の塗料の乗りのムラが発生するため、品質が大きく低下してしまいます。 (一斗缶を開封しないで缶を振っただけで混ざっていると誤解している職人さんもいますので注意が必要です。)
③については、必ず表示されている希釈剤を使用しなければなりません。極端な話として、油性の塗料を水で希釈しようとすると、水と油が反発しあい、全く希釈できないだけでなく、その塗料を使用することができなくなってしまいます。
④について、温度があまりに低い場合は凍結の可能性がありますので、水性の場合は5度以下の場合に塗装しないという注意文になっています。この項目については、油性の場合であっても、乾燥まで非常に時間がかかるため、低気温の場合の塗装はおすすめできません。
⑤以降についてはエアゾール式の塗料を使用する場合に関しての注意文となりますので、ここでは割愛いたします。
塗料の品質を維持する最も重要なポイントは、消費者庁が表示を義務付けている使用方法の4点になりますが、それ以外にも塗料の品質を維持するための使用方法があります。
1つめは、塗装を行ったのちにしっかりと塗料を乾燥させるという点です。外壁塗装に使用する塗料は、塗装が乾燥してから10年近く使用しますので、乾燥時の品質が高くなるように作られています。そのため、しっかり乾燥しないうちに中塗り・上塗りといった塗装の重ね塗りをしてしまうと、重ね塗りした塗料が混ざってしまい高い品質を維持できなくなります。そのため、各塗料に定められた乾燥時間をしっかり守り、かつ、プロの目から見てしっかり乾燥していると判断の上で次の工程に進まなければなりません。
2つめは、最低でも3回(下塗り・中塗り・上塗り)の重ね塗りを行うという点です。塗料は、基本的に重ねて塗るように作られています。どれだけ品質の高い塗料を使用したとしても、1回しか塗らなければ、その塗料本来の品質は発揮できません。そのため、最低でも下塗り、中塗り、上塗りの3回は塗装を行わなければなりません。外壁の状態や環境によっては、中塗りを2回、上塗りを2回など、各工程で複数回塗っても問題はありません。
外壁塗装の品質を決める最も重要な「塗料」ですが、ただ高価な塗料を使えば高い品質を得られるわけではありません。しっかりと使用方法を守って塗装する必要があります。
しかし、一部の業者では、残念ながら時間を短縮するためや、経費を削減するためといった目的で、使用方法をしっかり守らずに塗料を使用するケースも存在するようです。そのため、業者の選定は、塗装工事を依頼するうえで、非常に重要な項目となっています。